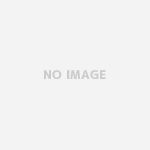今回は介護・福祉分野における「マンパワー」について説明します!
福祉マンパワーとは?
介護・福祉分野における「マンパワー」とは、ざっくり言えば「人手」であったり、「労働力」という意味で使われることが多い言葉です。
実際にマンパワーという言葉を使う場合、場面や状況によってその「範囲」が変動することもあり、いったいどこの範囲までがマンパワーと呼ぶのかは議論があります。
(たとえば、直接施設の利用者などに接する人だけを指すのか、全体をマネジメントする人なども含めるのか、施設に導入する用具や設備を作っている業者は含まれるのかなど)
なので、マンパワーという言葉を聞いてその範囲がはっきりしない場合は、すぐにその場で確認して認識を共有しておくのが重要ですね。
ただ、介護や福祉現場で活躍する人たちということもあり、各々が介護や福祉に対する専門的知識・技術をもっていることが特徴です。
主なマンパワーの大別について
場面や状況によって適用範囲があやふやになりやすいマンパワーですが、その範囲を性質ごとに4種に大別したものがあるのでご紹介します。
1、社会福祉関係法令にもとづく専門職員
4種に大別されたマンパワーの中の1つ目が社会福祉関係法令にもとづく専門職員です。
具体例を挙げると、社会福祉主事、児童福祉司、保育士、介護福祉士などの方々です。
これは、介護や福祉に関する専門的な知識やスキルを持っている人に限定して絞り込んだマンパワーの範囲と言えそうです。
2、法令の基づくが、無給である非専門的マンパワー
4種に大別されたマンパワーの中の2つ目が法令の基づくが、無給である非専門的マンパワーです。
具体例を挙げると、民生委員や身体障害者相談員などが挙げられます。
これは1つ目(社会福祉関係法令にもとづく専門職員)と法令の定めに基づいている点は共通していますが、無給に限定している点と、社会福祉関係の法令の範囲ではない方々が該当する点が特徴のマンパワーの言えます。
3、任意の活動で無給のボランティア
4種に大別されたマンパワーの中の3つ目が任意の活動で無給のボランティアです。
これはそのままの意味で、具体例を挙げるまでもないですね。
基本的に個人の意思によって行動するボランティアを対象としており、無給という点もポイントになりそうです。
4、シルバービジネス等有償福祉サービスの従事者
4種に大別されたマンパワーの中の4つ目がシルバービジネス等有償福祉サービスの従事者です。
これは特に法令の定めが関係しない点が特徴です。
サービスの従事者であれば該当するので、比較的範囲が広いことも特徴ですね。
これらが介護・福祉現場でのマンパワーの大別です。
実際に働くうえでは4種類すべてを覚える必要はないですが、ある程度イメージだけでも持っておくと咄嗟の状況で役に立つこともあるかもしれませんね。
おわりに
今回は介護・福祉現場における「マンパワー」について説明させて頂きました。
読んでいる中でお分かり頂けたかとは思いますが、福祉マンパワーは多数の職種、または様々な形態の職場の人々から構成されています。
そのため、繰り返しにはなりますが、その状況や場面によって柔軟に考える必要があります。
とは言っても、そこまで明確にマンパワーの定義や範囲が問題となることはないと思うので、心配しすぎなくても大丈夫だと思います笑
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします!