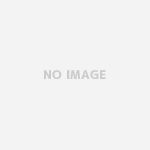今回は「心身障害者」について説明します。
心身障害者とは?
心身障害者とは、「身体または精神に相当程度の障害をもつ者」の総称のことです。
しかしながら、平成5年に心身障害者対基本法が障害者基本法に改められたことに伴って、心身障害者という表現は使用せず単に「障害者」と呼ぶことも多いです。
私の周りだとどっちも使われていますが、「障害者」のほうが聞く機会が多い気がします。
私自身も基本的には「障害者」を使ってますね。
障害者基本法に改められる前の「心身障害者対策基本法」を見てみた
気になったので、障害者基本法に改められる前の「心身障害者対策基本法」を見てみました。
心身障害者について記述されているのは主に心身障害者対策基本法の第2条にあります。
以下がその条文です。
心身障害者対策基本法第2条
第二条 この法律において「心身障害者」とは、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥(以下「心身障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
心身障害者対策基本法第2条を読むと、心身障害者に該当するには、
①肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害、言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥があること・・・つまり、身体的なハンデだけでなく、精神的な面も考慮するということですね。
②①が原因となって、長期間にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者
上記2つに当てはまる必要があるということですね。
まぁ、その障害の程度については人それぞれなので、ある程度ケースバイケースによるところもあるかもしれません。
なお、心身障害者扶養共済制度という制度に「心身障害者」という言葉が使われています。
(インターネットで調べると心身障害者扶養共済制度と障害者扶養共済制度の両方が出てくるから調べにくい(-_-;))
「心身障害者扶養共済制度・・・心身障害者を扶養している加入者たる保護者が死亡し、または重度障害となったとき、残された心身障害者に年金を支給する制度である」
要は、残された心身障害者を助けよう!という制度ですね。この制度も改正があったようです。
※蛇足かもしれませんが、東京都なども「心身障害者」という言葉を使用していました。
http://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kenko/shogai/nenkin/kyosai.html
最後に
今回は「心身障害者」についてまとめてみました。
調べている中で、法律の改正などによって大きな影響があるんだなぁと改めて実感しました。
今後とも、よろしくお願いします!