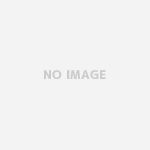今回は「インテグレーション」について説明します!
「インテグレーション」ってなに?
まず、「インテグレーション」の意味について説明します。
インテグレーションは、英語の「Integration」のことで、「統合教育」などと訳されます。
統合教育は『ウィキペディア(Wikipedia)』にて、以下のように記載されていました。
統合教育(とうごうきょういく)とは、健常者と障害者を同じ場所で教育すること。外来語では「インテグレーション」や「メインストリーミング」などが相当する。
要は、障害などのハンディキャップがある状態の人が、そうでない人と同じ環境で生活することにより、お互いの特徴を認め合ったり、より多様な価値観を育む機会になったりすることをねらったものが「インテグレーション」と言えます。
福祉や介護分野で使われる「インテグレーション」の意味合いは?
上記では一般的な「イミグレーション」の定義について触れさせて頂きました。
しかし、福祉や介護分野で使われる「イミグレーション」の意味は、上記の意味とやや異なる側面があります。
福祉や介護分野における「イミグレーション」には、大きく2つの意味を持っており、
- 地域のなかでハンディキャップをもった人が日常生活に支障をきたさないように、その地域で生活する住民や自治体、関連機関、団体などが中心となって問題解決に当たること。
- 社会福祉の対象者(シンプルにハンディキャップがある人と想定してもOKです)の処遇に当たり、その対象者がその他の健常者と差別なく、地域社会と密着した中で生活できるように援助をすること。
という意味を持ちます。
かなりざっくり言ってしまえば、「地域や社会が一丸となって障害などのハンディキャップがある人を支えよう!」「障害などのハンディキャップがあるからといって、健常者と同じように正当な評価がされるべきだ!」ということです。
「インテグレーション」の具体的な取り組みについて
「インテグレーション」を意識した具体的な行動として、さまざまな取り組みがされています。
たとえば、専門的な知識を持つ講師が各施設へ直接指導しに行ったり、地域での講習会などを実施したりといった活動があります。
これは専門的な知識を共有して理解を深めるだけでなく、改めて福祉サービスそのものを考えるきっかけになったり、今提供している福祉サービスを振り返るきっかけになることも考えられるので、全体的なサービスの質の向上につながることが期待できます。
他にも、国が推進している「地域包括ケアシステム」などもこのインテグレーションに該当すると言えるでしょう。(※地域包括ケアシステムとは、簡単に言えば、ケアマネージャや地域包括支援センターが全体的な調整役となって、さまざまなサービス・人をつなげていこうという仕組みです)
インテグレーションを進める上での注意点
これまでお伝えしたように、インテグレーションは現在の社会福祉を推進し障害者などを支える上で非常に大切で、基本的な理念・概念だといえます。
しかし、闇雲に知識や行動を増やすだけでは不十分であり、注意すべき点もあります。
たとえば、知的障害者に関する講習を受講したからと言って、安易にその内容をそのまま現場で実践するのはリスクが高いです。
もちろん、実践して上手く行く場合もあるでしょうし、結果的に上手くいけばそれで問題ないのですが、ひとことで「知的障害」といってもその範囲は広く、個人差も大きいことが予想され、上手くいかない可能性もあります。
特に、講習会などでは時間に限りもあるため、なかなか本質的な部分や深い部分の知識が習得できないケースが多いです。そのような状態で実践してしまうとかえって福祉サービスの質が低下してしまう危険性もあるので、実践する場合は一度冷静に考えてみるとよいですね。
このあたりはケースバイケースなので判断が難しい場合もありますが、いずれにせよ、サービスを受ける人の状態や援助体制、環境などに対する十分な配慮が必要になることを覚えておきましょう。
おわりに
今回は「インテグレーション」について説明しました。
今回この記事を書いていて、福祉や介護におけるインテグレーションの使われ方やその概念の重要性が改めて理解できました。
また、ケースバイケースで判断に迷う部分もありますが、その「迷い」も共有して解決できたら素敵だなぁと思いました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします!