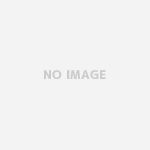今回は「残存機能」について説明します。
「残存機能」ってなに?
残存機能とは、障害のある方の障害以外の部分、つまり自分で活用することができる残された機能のことです。
例えば、脳梗塞などが発生した結果、一命を取り留めたものの左半身に麻痺が残ってしまった場合は右半身をはじめ、麻痺の影響がない部分が残存機能ということになります。
なお、片麻痺などの場合には健側(けんそく)・患側(かんそく)という言い方も使われますね。
一般的に障害があると、障害が発生した部分をはじめ、その影響で身体のさまざまな機能が低下することが多いです。
しかしながら、この残存機能を上手に活用することで、日常生活をしていくうえでの機能的なレベルをある程度保つことは可能です。(もちろん障害の程度によって個人差が大きいため、一概には言えませんが・・・)
残存機能は徐々に低下していく!
障害の程度にもよりますが、このように障害がある中で残された機能を有効に活用し、日々の生活を豊かにすることは可能です。
しかし、残存機能は使わないままでいると徐々に機能が低下してしまいます!
機能が低下するところは筋肉をはじめ、歩行する際の平行感覚や正確な距離感、関節の可動域など、物理面や感覚面を問わずさまざまです。
そしてやっかいなことに、一度残存機能が低下してしまうと低下した分の機能を取り戻すのにも時間がかかってしまう点にも注意が必要です。(リハビリと似てますね)
このようなことを考えると、障害者の援助にあたっては、被援助者の残存機能をできるだけ伸ばしていく、もしくは維持することを考えるのが重要であるといえます。
例えば介護施設などであれば、利用者ができることはなるべく利用者自身にやってもらうなどの配慮が必要となるでしょう。
そして介護者はそれを見守り、必要となる範囲で適切に利用者を支援していくことが望ましいですね。
いずれにせよ、障害者を支える際はなんでも手伝ってあげるのではなく、障害者の残存機能を最大限に生かしてもらえる様に側面から支えていくことが大切です。
おわりに
今回は「残存機能」について説明させて頂きました。
障害者自身の力で生活を楽にできるという点で、この残存機能をどう活用していくかは非常に重要です。
残存機能を低下させないためには、周りでサポートする方の理解や認識が必要になることも覚えておくと役立つと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします!